【THE世代感】80年代の学校映像に潜む4つの謎!「えび反り」「飛び込み」が消えた理由と時代の変化
目次
【THE世代感】80年代の学校映像に潜む4つの謎!昭和の常識は令和の非常識だった
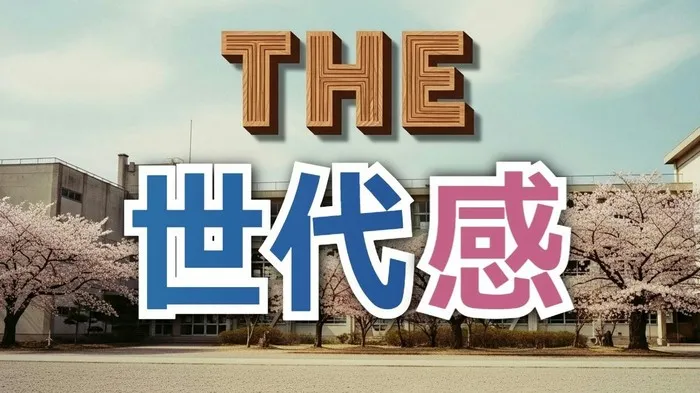 2025年10月25日に放送されたバラエティ番組『THE世代感』の「昭和の学校映像に映る今ではあり得ない違和感クイズ」は、世代間の常識の違いを浮き彫りにしました。
2025年10月25日に放送されたバラエティ番組『THE世代感』の「昭和の学校映像に映る今ではあり得ない違和感クイズ」は、世代間の常識の違いを浮き彫りにしました。
フットボールアワー後藤輝基さんとホラン千秋さんがMCを務める中、昭和の小学校の映像に、10代・20代が「どういうこと?」と驚愕した4つの大きな謎を徹底解説します。
かつては当たり前だった行動や習慣が、なぜ学校から姿を消したのでしょうか?その裏には、安全性の向上や技術の進化といった、時代を映す確かな理由がありました。
80年代の学校に潜む4つの「あり得ない」違和感の正体
若者世代が見て特に疑問に感じた、4つの違和感とその背景にある理由を深掘りします。
① 保健室で体温計を「振っている」
違和感: 10代・20代にとって、体温計はデジタルで自動的にリセットされるもの。なぜ振る必要があるのかが最大の謎でした。
謎の正体: 映像で使用されていたのは、水銀の熱膨張を利用した「水銀体温計」です。一度上がった水銀は自力で下がらないため、振って水銀を元の位置に戻す必要がありました。水銀体温計は環境への配慮から2021年に製造中止となり、現在では電子体温計が主流です。
② プールで「飛び込み」をしている
違和感:プールで飛び込みを指導していた時代があったことに驚きが集まりました。
謎の正体: 学校のプールは一般的に水深が浅く、飛び込みによって生徒が頭を底にぶつけ、脊髄などを損傷する重大事故が多発しました。この安全面のリスクから、2008年頃から小・中学校のプールでは飛び込みの指導が原則行われなくなりました。泳ぐ際は水中からのスタートのみとなっています。
③ 体力テストでなぜ「えび反り」?
違和感: 体力テストといえば「シャトルラン」や「上体起こし」などが一般的。「えび反り」のように背中を反る運動は見たことがない。
謎の正体: かつての体力テストには、背中側の柔軟性を測る「伏臥上体反らし」という項目がありました。しかし、この測定方法が腰に過度な負担をかけ、痛めてしまうリスクが指摘されたため、1998年に体力テストから除外されました。安全性を優先した結果、消えた測定項目です。
④ 登下校時に手荷物が異常に多い
違和感: 体操着、習字セット、絵具セット…と、両手いっぱいに荷物を抱えるかつての小学生の姿に、「なぜ全部持ち帰るのか」と驚きの声。
謎の正体: 以前は教材の自宅保管が基本でしたが、現在では「宿題で使わない教科書やノート」を学校に置いていく「置き勉」が多くの学校で推奨されています。その大きな要因が、タブレットの支給です。現在、GIGAスクール構想により生徒に1人1台支給されているタブレットは重く、これに教科書を全て加えると児童の負担が大きすぎるため、「置き勉」が推奨されるに至りました。利便性というより、IT化による重さ対策だったのです。
まとめ:安全性の向上とタブレット時代への変化
今回の『THE世代感』のクイズを振り返ると、昭和から令和にかけての学校生活の変化は、以下の2つの大きな流れによって引き起こされたことがわかります。
- 生徒の安全確保: プールへの飛び込み禁止や「伏臥上体反らし」の廃止など、事故や怪我のリスクを徹底的に排除する方向に舵が切られました。
- テクノロジーと利便性: 水銀体温計から電子体温計への移行、そしてタブレット導入による「置き勉」の普及は、デジタル化時代の利便性の向上と負担軽減を象徴しています。
過去の映像を見るとノスタルジーを感じると同時に、現代の子供たちが享受している「安全で快適な学校生活」のありがたさを再認識させられる、非常に興味深い企画でした。
親世代にとっては懐かしく、子世代にとっては新鮮な驚きとなるこれらの変化は、時代の進化そのものです。

佐々木竜千です。主に脳トレ謎解きクイズやRPG攻略、エンタメ、ニュースなどを発信しています。10年以上ゲーム攻略ブログを運営。読者の皆さんのスキマ時間の脳トレやゲームの疑問解決に貢献できるよう、日々情報収集と発信に励んでいます。



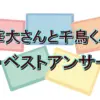
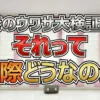

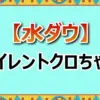

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません